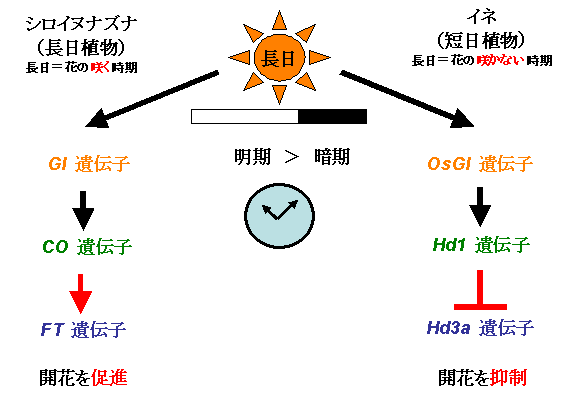
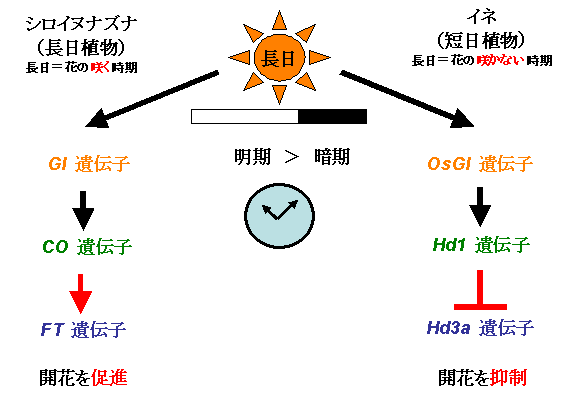
植物は自分の子孫を残す為に花を咲かせ種をつける。これは動く事の出来ない植物にとって、その場所で最も良い状態(日の長さ、温度などの環境条件)で花を咲かせ、種子を沢山つけるという非常に重要な戦略である。植物は子孫を残す為にいつ花を咲かせれば良いかという戦略を実行する過程で日の長さの変化(長日・短日)に対応して花を咲かせる機構を発達させてきた。昔から我々人類は長日植物・短日植物が存在する事を知っていたが花を咲かせる機構、すなわちどんな遺伝子が花を咲かせるのに必要であるか、何が長日・短日の違いを支配しているのかは知られていなかった。
近年のシロイヌナズナ(長日植物)の突然変異体の研究から、花を咲かせる為に重要な遺伝子のセット(3つの重要な遺伝子:GI, CO, FT)が存在する事が明らかになった。これら3つの遺伝子はGI - CO - FTという関係にあり、花の咲く時期にGI → CO → FT という正の方向の関係にある事が明らかにされた。
我々は短日植物のイネを材料に研究を行い、イネが長日植物であるシロイヌナズナと同じ遺伝子のセット(3つの重要な遺伝子:OsGI - Hd1 - Hd3a)を持ちながら、その調節機構のHd1からHd3aへの制御が負の方向に逆転している事を発見した。すなわち、イネ(短日植物)はシロイヌナズナ(長日植物)と同じ遺伝子セットを使いながら、その調節機構を逆にすることで日の長さに対する反応を反対にしていると言う事を明らかにする事が出来た。この発見によって昔から経験的にだけ知られていた長日植物・短日植物の違いを遺伝子レベルで示す事が出来たといえる。